リハビリテーションってどんな意味?
リハビリテーション(rehabilitation)はラテン語のre「再び」・habilis「適する」が語源で、中世ヨーロッパでは「名誉の回復」など、社会的な意味合いで使われていました。
「障がい(病気・ケガなど)に対する機能回復、能力向上、社会復帰」 という現在の意味で使われるようになったのは、第一次世界大戦で大量に発生した負傷兵のリハビリテーションがきっかけになります。
リハビリテーション医学という言葉(概念)が確立してきたのは1950~1960年代で、現在では「身体的・心理的・社会的・職業的・余暇的および教育的といった様々な面から、生活機能の回復を支援する」行為を指すようになりました。

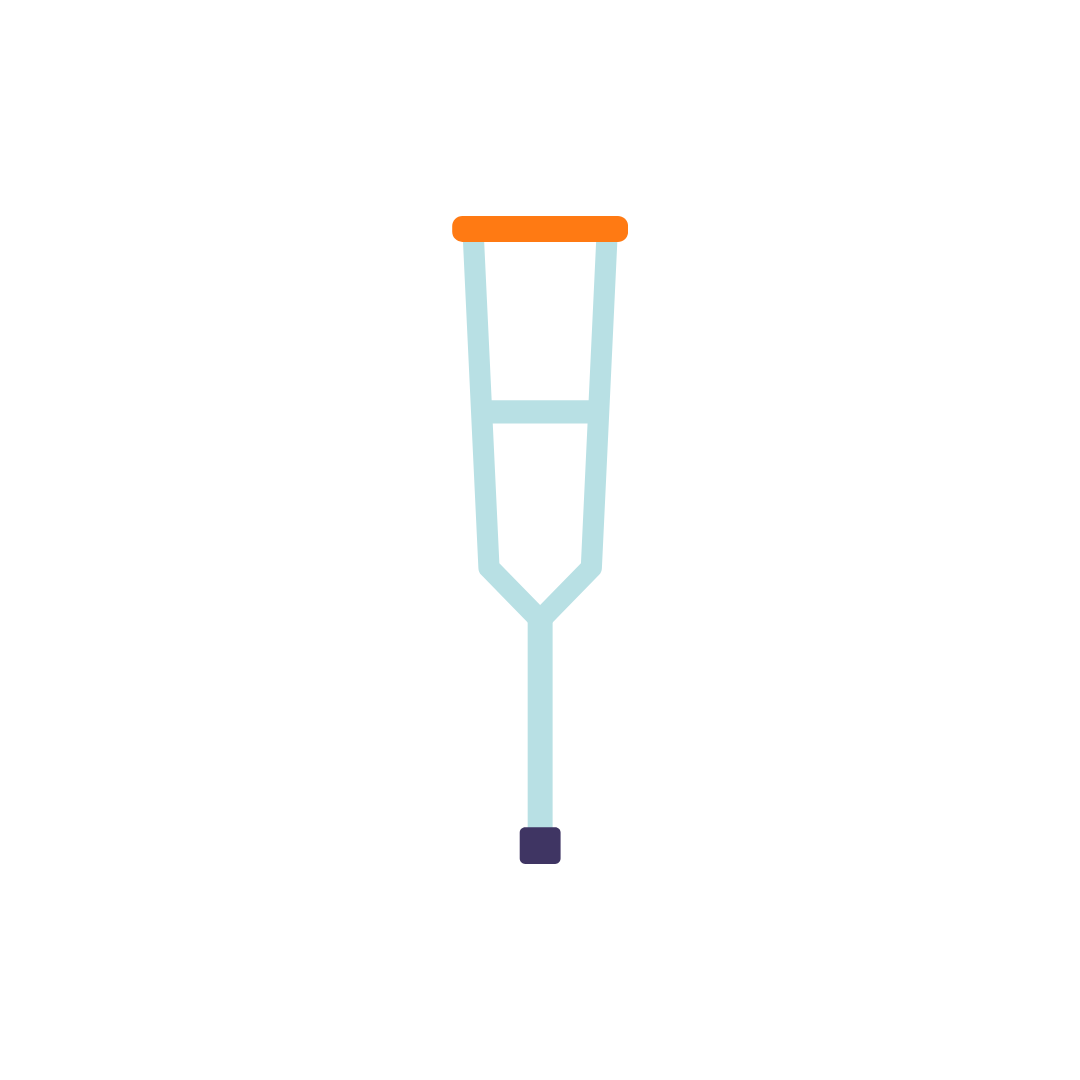 リハビリテーションの種類
リハビリテーションの種類
多くの皆さんがリハビリテーションだと思っているものは、医療リハビリテーションと介護リハビリテーションの二つに分けられます。
医療と介護の違いは、目指すものの違いです。
医療リハビリテーション:機能訓練に加えてQOL(生活の質)向上を目指す
介護リハビリテーション:日常生活の自立を目指す
医療リハビリテーションは病院や整形外科医院のリハビリテーション科、介護リハビリテーションはデイケアセンターや訪問リハビリテーションなどで行われています。
医療リハビリテーションは医療行為なので、医師の指示のもと行われます。
それに対し介護リハビリテーションは、正式には「リハビリテーションではなく機能訓練」となり、医師の指示は不要です。また、リハビリテーション専門職以外の職種の方でもサービスを提供できます。
それでは、リハビリテーションサービスを提供することができる職種にはどんなものがあるのでしょうか?ここでは、広い意味で機能回復訓練まで含めた医療系専門職を取り上げてみます。

理学療法士
理学療法士は、主に病院や医院のリハビリテーション科や介護施設、スポーツチームなどで「身体機能の回復」を目指します。体を動かすことによって機能回復を図る「運動療法」や、患部を温めたり、低周波をあてて筋の緊張をやわらげたり、マッサージによって血流改善を図る「物理療法」を行います。
作業療法士
理学療法士が「身体機能の回復」を担うのに対し、作業訓練士は、患者さんが「生活においてできるようになりたいこと」をできるようにすることを目指します。そのため、精神障害や発達障害も対象になります。リハビリテーションの内容も、実際の生活活動(作業=食事・選択・外出・手工芸など)をトレーニングとして行います。病院だけでなく、福祉施設での需要も高い仕事です。
言語聴覚士
言語聴覚士は「話す・聞く・食べる」といったことに障がいを抱える人を対象としたリハビリテーションの専門職です。脳卒中によって食べ物をうまく飲み込めない方、口腔がんの手術を行った方、言葉に関する発達の障がいがある方などが対象となります。口唇・舌・咽頭などの動きを改善する訓練や、脳機能障害によって失語症を患う方には、絵や文字などのカードを使用して、言葉を引きだすアプローチなどを行います。
視能訓練士
斜視や弱視の改善ための訓練計画を立て、管理・指導を行ないます。視機能が発達中の子どもを対象とする仕事となります。視能「訓練士」という資格ですが、視機能の訓練以外にも、眼疾患の検査・健康診断の検診、視機能低下者に対する補助具の選定や使い方の指導など、幅広い業務があり、約9割の人が病院や眼科医院などの医療機関で働いています。
義肢装具士
義肢装具士とは、事故や病気で失った手脚の役割を果たす「義肢」や身体をサポートする「装具」を作り、「適合」をおこなう医療専門職です。近年は、パラアスリートの競技用義手や義足を製作する職種として認知されるようになりました。義肢は患者さんの希望に応じたオーダーメイドが基本ですが、装具(コルセットやサポーターなど)は既製品を使用することもあります。約9割が補装具の製作事業所に勤務しています。
柔道整復師
柔道整復師は、骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの怪我に対して治療を行う外傷のプロです。一般的には「ほねつぎ」や「接骨師」として知られています。近年では「スポーツトレーナー」としてスポーツチームに所属して活躍している人も増えています。手技や包帯、テーピングなどを使って整復・固定・後療法(リハビリテーション)を行い、その回復を図ることが特徴です。独立開業ができる数少ない医療系資格のひとつです。一部の治療は保険の適用が受けられます。
鍼灸師
鍼灸師(しんきゅうし)は、鍼(はり)または灸(きゅう)を使い、病気の治療や予防などを行う医療技術者です。はり師ときゅう師は別々の資格ですが、両方の施術を行える人が多いため鍼灸師と呼ばれています。鍼灸治療院だけでなく、スポーツチームやスポーツジムなどでトレーナーとして働く人も多い職種です。鍼灸師も独立開業が認められている国家資格です。
あん摩マッサージ指圧師
あん摩マッサージ指圧師は「なでる」「揉む」「押す」「さする」などの手技を患者さんの身体に行うことで血行を改善し、不調を和らげる仕事です。鍼灸師の資格と同時取得を目指す人も増えてきました。主な活躍の場は、治療院・病院や介護施設などです。特に福祉分野で需要が高まってきています。独立開業も可能です。
整体師(カイロプラクター)
柔道整復師やあん摩マッサージ指圧師と間違えやすいですが、整体院・リラクゼーションサロンなどで働いているのが整体師になります。整体に関する民間の様々な資格を持った人の総称といえます。日本古来系・中国系・アメリカ系など、整体には決まった理論や技術はなく医療行為でもないため、整体の仕事そのものには、特に資格を必要としません。骨のずれなどを矯正することで筋肉のコリや疲労をほぐし、血行を良くするといった「症状の緩和・改善」を目的とするお店から、治療というより「もみほぐすことで体を癒す」ことが目的のお店まで様々なので、整体の仕事を目指す場合は「何ができる整体師」になりたいのかを事前に考えておく必要があります。
 リハビリテーションの仕事に就くためには
リハビリテーションの仕事に就くためには

これまでに紹介してきたリハビリテーション(機能回復訓練)関係の医療系資格は、国家資格のため、それぞれの資格の養成校で学ぶ必要があります。専門学校か短期大学で3年~4年、大学で4年学んで国家試験を受験する形になります。国家試験の合格率は以下の通りです。

令和5年2月実施の国家試験(柔道整復師は令和5年3月実施)
| 試験名 | 受験者(新卒者) | 合格者(新卒者) | 合格率 |
| 理学療法士 | 10,824名 | 10,272名 | 94.9% |
| 作業療法士 | 4,809名 | 4,390名 | 91.3% |
| 言語聴覚士※ | 2,515名 | 1,696名 | 67.4% |
| 視能訓練士 | 876名 | 821名 | 93.7% |
| 義肢装具士※ | 200名 | 162名 | 81.0% |
| 柔道整復師※ | 4,521名 | 2,244名 | 49.6% |
| はり師※ | 4,084名 | 2,877名 | 70.4% |
| きゅう師※ | 4,010名 | 2,875名 | 71.7% |
| あん摩マッサージ指圧師※ | 1,296名 | 1,148名 | 88.6% |




 学校の種類
学校の種類 地域
地域 なりたい仕事
なりたい仕事 学びたい学問
学びたい学問